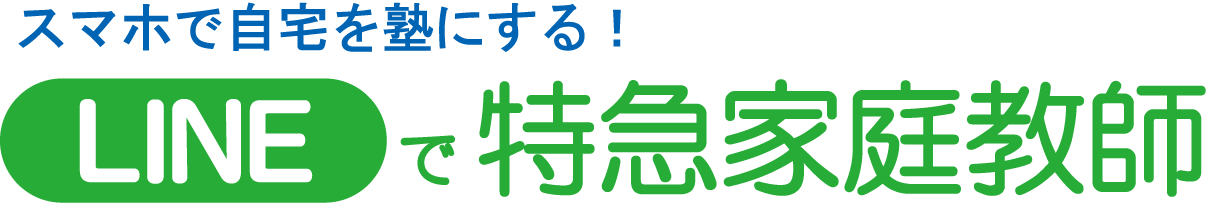「なんとか算」は,数と図を使った論理性を高めるための訓練と考えましょう.
●特殊算の背景
つるかめ算,旅人算,相当算…など,中学受験の算数では,多くの「なんとか算」がでてきます.これを「特殊算」といいます.
特殊算の歴史をふりかえると,江戸時代の和算や古代中国の算術まで関わる非常に深い話題なのですが,それはおいておきまして.
昭和20年台の小学校6年算数教科書と中学校1年数学教科書で,いつくかの特殊算(たとえば周期算や損得算など)が出てきます.
当時の中学校1年の数学では,動滑車の組み合わせや,てんびんなどのおなじみの問題も見られます.(昔は中学校数学であつかってたんですね)
このころの算数・数学(に限らずすべての教科で)は,日常との関連が非常に重視されており,「こういう場面ではこういう計算」という考え方でした.こういう時代では,場面によって使い分ける特殊算が生きていたのでしょう.
ただ逆に言うと,このころの算数は,場面によって計算方法をばらばらに学ぶだけでした.
現在では,算数・数学の教育体系はずいぶんちがいます.
高校数学に向けて,小学校算数と中学校数学をどのように体系的に学ぶか,という考え方で,全体の体系(ビジネスの世界ではロジック・ツリーとよばれる考え方が近いかもしれません)がつくられています.
特殊算の多くは,方程式を使って解けるために,散発的で体系的ではないと考えられ,だんだん主流からはずれていったのではないでしょうか.
また,特殊算は難易度が高いため,子どもの実態に合わせて公立学校ではあつかわれなってきたのかもしれません.
一般的に特殊算を使う問題の多くは,中学校で学習する連立方程式(と文章問題から連立方程式を組み立てる力)を使って解けます.
連立方程式という1つの強い武器があれば対応できるのです.
わざわざ特殊算ごとの解法を暗記し,問題ごとに解法を当てはめて…というやりかたは数学の本質とは言えません.
であれば,小学校で難しい特殊算をわざわざ学ぶのではなく,連立方程式まで学習を積み重ねてしまおう,というのが現代の一般的な算数教育です.
ところが,この特殊算が生き残ったのが中学校受験です.
中学校受験は,小学校で学習した内容を応用すれば解ける,という建前があります.
言い換えれば,中学校の数学を使わずに問題を難しくするにはどうするか.
その結果,小学校でも中学校でも扱わず,中学校の学習内容とは言えない特殊算が使われるようになったのではないでしょうか.
しかし,算数・数学教育としては,特殊算のパターンを覚えることは非効率であると考えられます.
また,特殊算は中学校以降まったく出てきません.
では,やらなくてよいのでしょうか?無駄なのでしょうか?
無駄でないという根拠はもっていないのですが,思考訓練としてはそれなりに役に立つ,というのが一般的な解釈です.
特殊算は,図・数直線・表などを使って,連立法的式などを使わずに,答えを導く方法です.
それ自体は,数学的センスや論理的思考力を鍛える効果があるでしょう.
また,特殊な解法といえども,数字をあつかうことが得意なお子さんは,やはりできます.
算数の力を測るためには,結局中学受験であつかわれ続けるはずです.
中学受験の算数対策として,連立方程式がなぜ主流にならないのかというと…よくわかりません.
中学校受験の,小学校で学習した内容を応用すれば解ける,という建前はあるのですが,そもそも理科と社会は,この建前は機能していません.
だったら算数も,もう中学校数学レベルでいいのではと思いますが,そうはならないようです.
いずれにしろ,基本的には大手塾では連立方程式は教えません.
ただ,個別指導や家庭教師のレベルだと,個人的に説明していることも多いようです.
一方で,子どもたちに統一して連立方程式を教えてしまえば解決かというと,そう簡単でもないようです.
連立方程式を理解するには,その基礎となる考え方がいろいろありまして,今はそれを中学校数学の1年間で学習します.
塾でそのまま前倒ししようと思っても,難解だったり,定着の時間が足りなかったりするでしょう.
それに,連立方程式に対する小学生の反応を見ていると,数式を解くことはできるのですが,文章問題からxとyを使った数式を立てる過程が相当難しいようです.
もしかしたら,発達段階としては,文章問題から式を立てるより,特殊算の方があっているのかもしれません.調査結果があるわけではなく,感覚的ですが.
●入試で連立方程式は使ってはいけないの?
入試で採点する側の先生に聞いたところ,そこまで気にしていないそうです.
解答用紙に連立方程式を書いてあったからといってバツにしたりはしないと.
特に都内の入試では,多数の解答用紙をチェックして,その日のうちに合格者を公表しますので,解法まで判断基準にする時間の余裕はありません.
ただ,これを聞いたのはごく一部の私学の先生です.学校によってはバツといううわさがありますのでご注意ください.
もう一つ注意点です.
お父様がご家庭でお子さんを教える「パパ塾(父能研ともいうそうですが)」では,連立方程式を教えて,かえってトラブルになったという話題が絶えません.
大人からすれば,そちらの方がはるかに解きやすいので当然とは思います.
ただ,中途半端にお子さんに説明すると,塾の解法とあまりにちがうので,かえってお子さんが問題を解けなくなったり,ということが起こります.
お父様が,小学校6年までの算数をふまえ,中学校の内容を段階的にお子さんに説明できるなら,かつ,お子さんがついてこれそうなら,連立方程式もよいでしょう.
ただ,お父様がずっと面倒を見ることができず,中途半端になる恐れがあるのなら,やめておくことをお勧めします.
家庭教師の先生などがきっちり説明を終えられそうなら,それも可能性かもしれません.
ちなみに,多くの塾では特殊算のテクニックから教えないことが多いようです.これは,テクニックを身に着けてしまうと,いざ問題を解くときに,「どのテクニックを使えばいいか」から考えてしまい,かえって柔軟性がなくなるため.
それよりは,問題文をきっちり算数的に考えて図や数直線などにできる力の方が大切です.